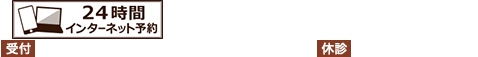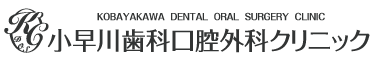自律神経との咬合自律神経の関係
歯は周りの組織にある組織、舌、顎関節、唾液、唇、口蓋などと連動して機能される「口腔」という臓器の一部でありほかの臓器とともに自律神経と関わっています。唾液の分泌量、口腔粘膜の免疫応答、咀嚼筋の開閉時のコントロールなど自律神経がうまくいかないと口の乾燥、口臭や歯周病、虫歯、咀嚼筋の筋肉や顎関節の痛み、緊張性疼痛などを引き起こす。又かみ合わせがズレたり、矯正治療の一部でかみ合わせに不都合が生じたりすると自律神経失調症に陥るケースもある。又食いしばりなどによる筋肉の持続的な緊張も自律神経に対して弊害をもたらす。筋肉の緊張が持続すると副交感神経優位になれず不眠、動悸、消化不良を引き起こす。「歯ぎしりは左右の歯をこすり合わすことで下顎の範囲が側方にかかるので奥歯に過剰な側方にかかるので歯や周囲組織の疾患を引き起こす。一方「食いしばり」は上下の歯をあて続けることで歯に垂直な力で筋肉に過緊張を続けることになり顎関節症や不定愁訴につながります。かみ合わせが悪いと顎や後頭部の筋肉が緊張し首や肩、背中が凝ってきます。筋肉がかたくなれば背中の柔軟なたわみがなくなり後頭骨や蝶形骨の動きが止まり脳に良い刺激が伝わらなくなり自律神経だけでなく視床下部や脳下垂体において内分泌の機能が狂ってきます。傷害性咬合から理想的予防咬合にしてリハビリメンテナンス。
2025年04月10日 04:32