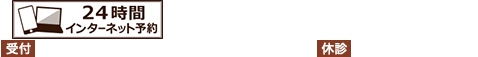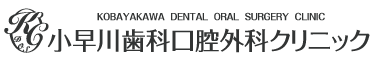口腔内トラブル
口のなかのことを口腔といいます。口腔には臓器が歯、下顎骨、上顎骨、顎関節、頬粘膜、舌、口蓋垂、咀嚼筋などの臓器があり機能として食事する、呼吸する、発音するなどがあります。歯並びや咬みあわせが眼とか鼻とか耳などのようにシンメトリックであれば理想でありかつ美しいものであるが残念ながらそうでない人が多いのが現実である。口腔に関してのトラブルはいろいろありますが歯痛、歯茎の痛み、口内炎、舌腫瘍、顎関節、片頭痛、頸肩腕症候群、粘膜疾患などありますがその中で一番多いのは歯痛よりも歯茎の痛みです。例えば歯が凍みるというトラブルです。ところがレントゲンで撮っても悪くないし、器質的変化もないしどこも悪くないと言われたことありませんか?次に虫歯などの歯痛で神経を取った歯が何か月後再び腫れたり痛かったりしませんか?あるいは同じ歯が何度もとれるこがありませんか?次に歯の処置をたくさんやっている人は肩こりとか顎が痛かったりしませんか?ではこのような口腔トラブルが発生するのでしょうか?細菌以外だと力の問題が考えられます。つまり【咬みあわせの問題】です。咬みあわせが悪いと口腔の中の一部に偏った力がかかり続けます。そうするとその力が受ける歯や粘膜や顎関節、歯突起などが障害を起こし(障害性咬合)。歯の場合だとひびが入りそこから異物が入り(マイクロクラック)いわゆる虫歯になったり、それが進行すると歯の根に炎症が広がり、神経を取ることになったり、歯茎にある歯根膜が障害を起こし凍みたりさらに歯を支える骨が歯周病になったりします。歯のトラブルは細菌だけでなく力の問題であることが多いのです。しかし実際は臨床では矯正したりして咬みあわせもよくなっているはずだし歯並びも比較的に整っているのに咬みあわせが悪いのですか?という質問には理想のかみ合わせは両側の4番(第一小臼歯)が「リトルーシブ・ガイダンス」になっているかということです。(又は犬歯誘導)矯正は抜くことが多いし、歯並びがよくても第一小臼歯のかみ合わせがうまくいってないと6番7番が「リトルーシブストップ」にならないから咬合性外傷を起こすことになる。つまり車で例えるとハンドルであったりブレーキであったりする調節の機能があります。従って左右の咬合の安定を図ること(咬合のコントロール)と(プラークコントロール)のバランスが崩れると口腔内トラブルが起こります。それから視床下部に行き自律神経やホルモンのバランスが崩れていろんな全身的な病気に発展する一方でプラークコントロールの乱れで歯周病として血管を通して全身に行きます。
2025年07月07日 04:05