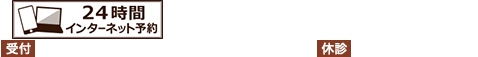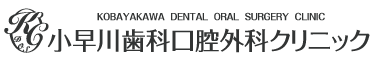②癌患者を診る前に看護で用いられる口腔アセスメント
口腔内の評価、予防的介入を効果的に行うことにより、多職種で問題点を共有し、口腔内の有害事象の早期発見と症状悪化の抑制に努め癌治療計画の中断を最小限に抑えます。多職種で治療期間中の口腔内の維持管理・変化を継続的に観察していくには、口腔ケアアセスメントツールがあると統一した指標になります。【全身評価】(癌治療方針)、(全身状態)、(既往歴)の確認を行う。治療方針は根治的治療と緩和的治療に分けられそれぞれの目標の設定地点が異なるため設定に適した介入が必要となります。全身状態は頭頚部のPSスケールは会食・食事内容・会話の明瞭度で評価します。既往歴では脳血管障害や糖尿病などは易感染性や止血困難など注意が必要である。臨床検査データーや服用薬を調べケアの妨げになる要因が存在しないか確認します。【口腔内評価】病態進行度アセスメント、放射線口腔アセスメント、緩和医療口腔アセスメントに分けられます。(口腔内衛生状態)口腔管理の不備により術後合併症・粘膜炎から感染リスクが上昇するためプラーク・歯石の付着やブラッシング回数、口臭の有無があるかを確認します。(歯の植立状態)口腔内に高度動揺歯、易脱離の補綴物がないか確認します。誤飲の可能性があるため除去または固定の必要性あり。歯肉に排膿がある場合は化学療法により歯性感染症のリスクが高まるため注意します。(粘膜の評価)口内炎は化学療法、放射線療法により多く出現するので注意する。(味覚)化学療法、放射線療法により味蕾の閾値の変化やダメージを受け味覚障害が出現します。(口腔乾燥)治療によって唾液線腺房細胞がダメージを受け唾液の分泌量が低下する場合があります。脱水や全身状態の悪化によって口腔乾燥があるかないか観察します。(開口量)治療後創部痛や組織線維化により開口量の減少が考えられる。(嚥下状態)意識レベルや残存している摂食嚥下の機能を十分に理解し、口腔ケアによる誤嚥の可能性を踏まえ安全な姿勢を保持できるかを評価します。
2025年10月18日 13:33