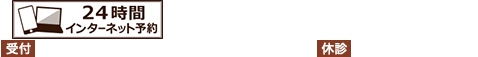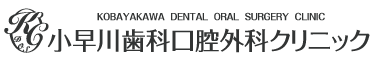頭頚部がん放射線治療患者の口腔管理・口腔ケア①放射線治療による口腔合併症
【放射線粘膜炎】放射線による粘膜炎は最も苦しめる合併症です。頬粘膜、舌縁、軟口蓋に好発し疼痛だけでなく口腔・咽頭の機能障害を起こし、低栄養や誤嚥を引き起こす。照射開始7日ごろから出現し、二次感染等がはければ14日ほどで消失しますが併用化学療法の有無で重篤度が異なり休止や中断を招く高度なものは放射線だけでは35%、化学放射線で45%認められます。治療薬はサルコート、レパミド、スルファサラジンの内服など。金属修復物や矯正装置がある場合はこれらが照射野にある場合は放射線が金属に接すると錯乱し粘膜染料が増強します。その場合はシーネを作ったりして防御します。【唾液分泌障害と味覚障害】これらもほとんどの患者さんが訴える合併症である。唾液分泌障害は線量30~40㏉が回復の限界である。対応としては唾液分泌剤としてピロカルピン®サラジェンの処方。味覚障害は栄養状態や治療意欲を低下させるのでしっかり対応しなければなりません。異常の程度は放射線による味蕾の萎縮や唾液分泌低下や舌苔の付着も影響されるので保湿と舌磨きは必要です。ポラプレジンク®プロマックの必要性があります。
【放射線顎骨壊死】放射線顎骨壊死の発生率は約7%とひくいものの疼痛、機能障害、顔貌の変化を引き起こす。下顎臼歯部に好発し治療後6か月以内と3年以降に発生することが多い。その中でも抜歯後顎骨壊死の発生率が高く最大のリスク因子です。これは放射線による骨細胞の減少、血流減少、低酸素化が顎骨に生じ、顎骨の易感染化と創傷治癒不全が引き起こされるからである。組織変化は回復しません。それでも困難な場合は高気圧酸素療法と顎骨離断術が行われます。
2025年11月05日 08:32