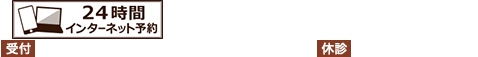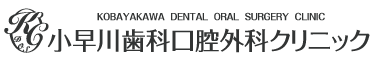薬剤関連顎骨壊死(MRONJ)
【顎骨壊死を引き起こす可能性のある薬剤】①骨吸収阻害剤・・・注射剤であるビスホスホネート製剤は悪性腫瘍に伴う高カルシウム血症、多発性骨髄腫、固形癌の溶骨性骨転移の治療に用いられて経口BP製剤は骨粗しょう症あるいは骨密度の低下に対する治療薬として用いられている。癌治療におけるBP製剤の投与は注射剤であるが長期間のホルモン療法がおこなわれていある場合は経口のBP製剤が用いられています。抗RANKL抗体であるデノスマブは破骨細胞の機能を障害することで骨吸収を抑制します。多発性骨髄腫や固形癌の骨転移に4週間ごとに皮下注射を行いますが骨粗鬆症として用いられる場合は6か月に一度皮下注射します。②血管新生阻害薬・・・血管新生阻害薬は血管新生にかかわる様々なシグナル分子に結合することにより血管の新生を阻害します。スニチニブ®スーテント、ソラフェニブ®ネクサバール、ベバシズマブ®アバスチン【顎骨壊死の診断】①顎骨壊死の診断所見・・・骨露出や顎骨の疼痛や排膿。下顎オトガイ部の知覚異常(Vincent症候群)抜歯や義歯不適合による歯肉潰瘍などにより粘膜欠損、骨露出により発生することが多いです。②診断基準・・・(1)現在、過去に骨吸収阻害薬による治療歴がある(2)顎骨への放射線照射歴がない。(3)口腔、顎、顔面領域に骨露出や骨壊死が8週間以上続いている。③発生頻度・・・BP製剤1,3%デノスマブ1,8%経口BPは0,01%~0,02%。④原因・・・骨リモデリングの変化、骨吸収抑制、微小骨片、ビタミンD欠乏、細菌感染、血管新生の抑制、血管閉塞、血流低下などあるが未だ解明されていない。
【顎骨壊死の治療】治療の原則は保存的アプローチとされています。抗菌薬投与、疼痛や知覚異常の緩和や感染制御、口腔内清掃の徹底と局所の洗浄など。抗菌薬はβラクタムが第一選択。クリンダマイシン、ニューキノロン系の投薬。顎骨壊死ではアモキシシリン、クリンダマイシン、レボフロキサシン。顎骨壊死発生時の休薬はがん患者の場合は骨転移による疼痛の緩和と病的骨折の予防であるためBP製剤の投与は続けます。経口BPの場合は中止。
【BP製剤、デノスマブ、血管新生阻害薬投与患者に対する口腔ケアの注意点】
①薬剤投与前・・・開始後の抜歯、歯科インプラント埋入、歯周外科、歯根端切除などの侵襲的歯科治療は顎骨壊死のリスクを高めるので少なくとも投与2~3週間前に終わらせることが必要となります。
②薬剤投与開始後・・・定期的に口腔内清掃を行います。歯科一般処置は薬剤投与中でも必要に応じて行います。
③口腔外科処置と休薬・・・注射用BP製剤投与の患者に口腔外科処置を行う場合は原則的にBP製剤の投薬は継続します。経口BP製剤は投与3年未満リスクファクター(-)の場合は休薬しない。投与3年以上あるいは投与3年未満かつリスクファクター(+)は休薬が望ましい。BPを休薬し口腔外科処置を行った場合の再開は2か月目が投与の再開になります。しかし早期に再開が望まれるなら抜歯窩がほぼ上皮で閉鎖され、感染の疑いがなければ2週間目で投与が可能とされています。
2025年11月07日 11:20