歯の痛みの伝導経路
受容器(歯髄、歯根膜知覚神経終末)⇒三叉神経Ⅱ枝Ⅲ枝⇒半月神経節【第1次ニューロン】⇒歯根膜枝(三叉神経上知覚核)と歯髄枝(三叉神経脊髄路核)に分かれるが歯根膜の方は三叉神経背側2次上昇路。歯髄の方は延髄、橋、中脳を通って三叉神経腹側2次上昇路。⇒三叉神経毛帯⇒視床の後内腹側核(VPM)【第2次ニューロン】⇒大脳皮質の頭頂葉の中心後回にある体性感覚領に達している。
2025年12月28日 08:14
呉市広駅前 小早川歯科口腔外科クリニックでは、歯科口腔外科・小児歯科・審美歯科・インプラント・レーザー治療など幅広く対応します。
ホーム ≫ ブログページ ≫
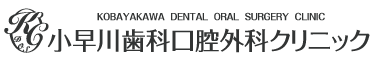
呉市広駅前|歯医者
小早川歯科口腔外科クリニック
〒737-0142
広島県呉市広駅前1-8-11
TEL:0823-72-3041
受付時間:月~土
AM/9:00~12:30
PM/14:00~19:00
土曜午後の診察は17:00まで
休診日:木曜午後、日曜、祝日
スマートフォンからのアクセスはこちら