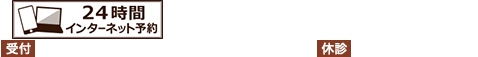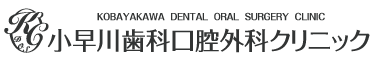1⃣トポイソメラーゼ阻害薬・・・・DNAトポイソメラーゼは細胞核にある酵素である。DNAのねじれを修正する酵素である。DNAはトポイソメラーゼで切断されたのちDNAとこの酵素は共用結合を起こします。そして切断されたDNAの立体構造が適切に修正されたのちDNAは再度結合します。トポイソメラーゼ阻害薬は上記のDNAの切断ー再結合反応を阻害させることにより、細胞分裂を停止させ、結果的にアポトーシスを起こして細胞死に至らせる。Ⅰ型(TOPO1)は二重らせんの一方を遮断しⅡ型(TOPO2)は両方とも切断します。前者はイリノテカンは大腸癌や肺癌など。後者はエトポシド、アントラサイクリン系のドキソルビシン®アドリアマイシンはDNAに結合(インターカレーション)、ダウノルビシン、エピルビシン、アムルビシンなどがある。【副作用】骨髄抑制
2⃣白金化合物・・・DNA鎖に結合⇒DNA転写、複写できず⇒癌細胞縮小。G-G、G-Aに結合。第一世代シスプラチンなど。第二世代カルボプラチン、第三世代オキサリプラチン、大腸癌。【副作用】(骨髄抑制。)カルボプラチンは血小板減少。(嘔吐、嘔気。)5-HT3受容体拮抗薬®ガスモチンNK1拮抗薬アプレピタント。D2受容体拮抗薬®プリンペラン®ナウゼリン(腎毒性)帆液による利尿。
3⃣代謝拮抗薬・・・抗がん剤のなかで主に細胞内の酵素に作用してDNA,RNAといった核酸の代謝経路を阻害する薬剤を代謝拮抗薬といいます。葉酸代謝拮抗薬、ピリミジン代謝拮抗薬、プリン代謝拮抗薬。
①葉酸代謝拮抗薬・・・・葉酸⇒ジヒドロ葉酸⇒テトラヒドロ葉酸⇒DNA合成®メトトレキサート、ホリナートCA(MTX副作用予防)ジヒドロ葉酸還元酵素阻害,ペメトレキセド
②プリン代謝拮抗薬・・・6-メルカトプリン(チオイノシン酸)アデニン、グアニンになれずDNA合成複写阻害。白血病の治療
③ピリミジン系代謝拮抗薬・・・5-FUはピリミジン代謝拮抗薬の代表的な薬剤。5-FUは体内で5-FdUMPに変換されこれがDNA合成に必要なチミジル酸合成酵素(TS)と結合することによりdUMP⇒チミジル酸⇒DNA合成阻害。
テガフール、カペシタビン®ゼローダ、TS-1(5-FU,ギメラシル、オテラシル)。【副作用】骨髄抑制、間質性肺炎、肝障害、腎障害
シチジン系・・・シタラビン⇒AraーCTPシタラビン3リン酸でDNAポリメラーゼ、ゲムシタビン⇒dFdーCTPジフルオロシチジン3リン酸でDNAに取り込まれDNA合成阻害。
4⃣微小管阻害薬・・・ビンカアルカロイド系ビンクリスチン。チュブリンの重合を阻害し微小管の崩壊。タキサン系パクリタキセル、ドタタキセル。チュブリンの脱重合を阻害して微小管の伸張に向かわせる。【副作用】神経障害
5⃣アルキル化剤・・・シクロホスファミド®エンドキサン。DNAと強固に結合して(グアニン、アデニン)架橋を形成しDNA
複製を妨げる。【副作用】骨髄抑制
6⃣抗腫瘍性抗菌薬・・・ドキソルビシン®アドリアマイシン、ダウノルビシン、ブレオマイシン、マイトマイシンC、アクチノマイシンD【副作用】間質性肺炎
7⃣分子標的薬・・・「癌細胞の特異的な標的分子に対する特異的な作用」
モノクローナル抗体と低分子化合物(標的分子は変異遺伝子か融合遺伝子産物であることが多い。)
(1)抗EGFR抗体・・・セツキシマブ、パニツムマブ EGFR阻害薬(小分子)ゲフィチニブ(非小細胞肺癌)
(2)HER2抗体・・・トラスツマブ、ベルツズマブ HER2阻害薬ラパチ二ブ、エルロチ二ブ
(3)抗VEGF抗体・・・ベバシズマブ 抗VEGFR2抗体・・・ラムシルマブ VGEFR阻害薬アキシチニブ
(4)BDR-ABL阻害薬・・・チロキシナーゼ活性阻害薬・・・イマチニブ(慢性骨髄性白血病)ダサチニブ
(5)mTOR(エムトア)阻害薬・・・エベロリムス(セリン・スレオニンキナーゼ活性阻害)FKBPと結合。副作用】間質性肺炎
8⃣ホルモン療法・・・①ホルモンの放出を抑える②受容体ブロック③合成を抑える
①LH-RHアゴニスト・・・リュウプレリン、ゴセレリン
②受容体ブロック・・・抗エストロゲン・・・タモキシフェン 抗アンドロゲン薬フルタミド
③アロマターゼ阻害薬・・・アナストロゾール CYP17阻害薬・・・コレステロール⇒アンドロゲンを阻害アビラテロン
2025年10月20日 13:56